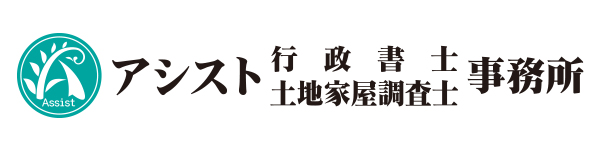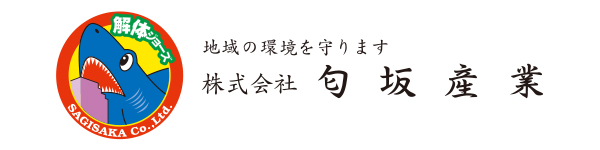配布中のニュースレターの内容をボリュームをアップし、下記にブログ記事としても掲載しています。ブログ記事で読みたい方は目次から気になるところをチェックしてみてください。
天然芝だからこそ得られる運動感覚

8月は7月の雨が続いた天候と違って、ほぼ毎日太陽の日差しが照り付ける猛暑日が続きましたね。
9月は残暑が残りますが、少しずつ過ごしやすい秋の季節になっていくことを願っておきましょう。子どもたちがサッカーを思う存分楽しめる環境づくりを続けていきます。
さて、写真は8月のお盆休み前の一コマ。大藤小学校の天然芝をかりてトレーニングを行いました。
天然芝だからこそ得られる運動感覚を体にため込んでいる様子で子どもたちの動きもダイナミックになっていました。
運動あそびでキャベツになった男の子

浜松市内こども園でのリーベ運動あそびの一コマをちょこっとご紹介します。
ヨガマットの上で動物ダンスをした後に、年長の男の子がマットで自分を包み込み写真のような格好に。「それなに?」とコーチが聞いてみると「キャベツ!!!」と自信満々な表情で教えてくれました。
ヨガマットを使ってキャベツになるなんて大人の発想ではなかなか思いつきません。やっぱり「子どもの発想力や創造性は豊かで面白い!」
遊びで培われた力はどこかで繋がって力になっていくでしょう!次回の運動あそびも楽しみになりますね。
袋井市内幼稚園で保護者講演会

少し前になりますが、7月9日(木)に袋井市田原幼稚園で袋井市親スキルアップ事業保護者講演会でお茶コーチこと高橋亮祐コーチが講師を務めました。
我々、クラブが大切にしている「遊び」がなぜ必要なのか?を講和と実践を交えながら60分間、田原幼稚園の保護者の方々へお伝えしました。
幼稚園の先生方も写真のように椅子と椅子を離して、感染症の対策を徹底しながらの講演会となりました。
保護者から「”こうなってほしい”という大人の気持ちを押し付けずにありのままの成長を受け止めて見守っていきたいと思いました。遊びの時間を大切にしていきたいです。」という感想も頂きました。
下記では、ニュースレター②スポーツコミュニティ広場で発信している内容になります。生涯、人生を豊かに過ごしていけるように大人と子どもの心と体をテーマに情報をお届けしていきます。9月号は7月の保護者講演会でお伝えした「遊び」がなぜ必要なのかを簡単にお伝えしていきますので目を通してもらえると嬉しいです。
そもそも遊びってなに?
「遊び」という言葉だけ聞くと、人によってイメージするものがバラバラだと思います。
そこで我々は遊びとは何か?を定義づけすることによって遊びの価値を創造していこうと考えました。
ポーラスターの考える遊びとは、
- 自発的である
- 好奇心を持って、チャレンジする
- 楽しいと感じ夢中になる
の3つが揃っているときが遊んでいる状態だと定義しました。
遊びはありますか?遊びはゆとり
遊びの3つの定義にあと一つだけ付け加えたい考え方があります。それは遊びは”ゆとり”であるということです。
「遊び」という言葉を国語辞典で調べてみると、物事にゆとりがあること、機械など急激な力が及ぶのを防ぐため部品の結合部にゆとりをもたすこと、などとも書かれています。我々の求める”遊び”もこのゆとりや余裕のことです。
例えば、自動車のハンドルには”遊び”と言われるゆとりを持たせてあります。ゆとりがないとハンドルを切った途端にタイヤが動いてしまい車を制御できなくなってしまいます。
つまりこの”遊び”があることで余裕をもってスムーズに曲がれることが出来ます。我々は、サッカーなどのスポーツにもこの余裕、いわゆる遊びが必要だと考えています。常に「勝ち」「負け」や「できた」「できない」だけの評価だけでは息が詰まってしまいます。
まずは、大人が心に遊びを持たせて子どもたちに関わっていけるような環境づくりを目指していきたいですね。
アへフフの時代に必要な遊び
アへフフって何?!と感じた方に解説します。
アへフフとは、曖昧性・変動性・複雑性・不確実性の頭文字をとった造語です。一般的な言い方だとそれぞれの英語の頭文字をとって「VUCA」(ブーカ)と言われています。
VUCA(ブーカ)とはV(Volatility)変動性・U(Uncertainty)不確実性・C(Complexity)複雑性・A(Ambiguity)曖昧性の頭文字をとった造語。
豊かなスポーツライフをサポートする情報誌 Sport Japan Vol.49 [特集]ご存知ですか?AI時代に問われる「非認知能力」をスポーツが育む理由 ページ7 これからの時代に求められる「非認知能力」って、何だ?! 遠藤利彦(東京大学大学院教育学教育研究科教授)
「アへフフ」だと音の響きですぐに覚えられそうだったので変えてみました。ちょっとした遊び心です。
それでは本題へ。
今、読んでくださっているあなたも感じているように、このご時世、未知の感染症の広がりやAI技術の発展・大きな気候変動によって地球規模で予測のつかない時代になってきています。
常に状況は変化し、様々なことが複雑に絡み合い、正解のない、曖昧な日々が続いているように感じます。
そんな時代を生き抜いていくために今の子どもたちには、より一層、遊びが必要になってきます。
特に幼少期の遊びは非認知能力が培われると言われています。
学力の経済学(著中室牧子)によると社会に出た時に必要なものは、学力テストのような評価、いわゆるIQの高さよりも、非認知能力と言われる社会性・粘り強さ・自己肯定感などが大切だと述べられています。
非認知能力は、認知能力の形成にも一役買っているだけでなく、将来の年収・学歴・就業形態などの労働市場における成果にも大きく影響することが明らかになってきたのです。
「学力」の経済学 著者:教育経済学者・中室牧子
もちろん、学力も大事ですが、遊びを通して非認知能力を高めてくと将来、社会的にも経済的にも豊かになるという研究結果が出ています。だからこそ、大人も子どもも遊びを大切にして日々の生活を送ってほしいと我々は考えています。