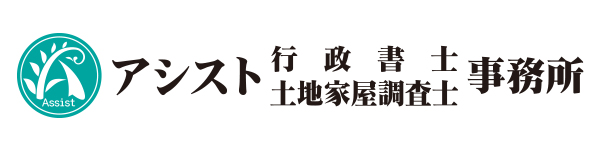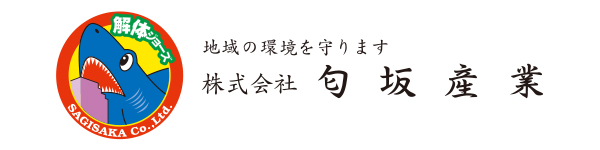こんにちは!
くもりの日がつづいて偏頭痛なお茶コーチことポーラスターの高橋亮祐です!
保育園や幼稚園で働いている先生方から幼児の運動面でこんなお悩みを聞くことが増えてきました。
 先生
先生幼児期に跳び箱・鉄棒・マット運動ができないまま卒園してしまうことに困っている。
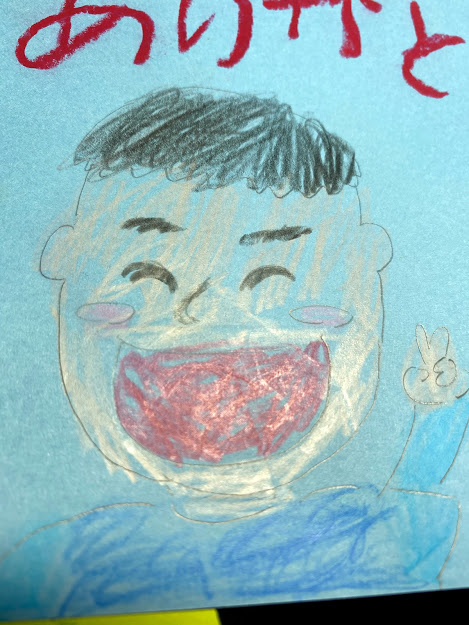
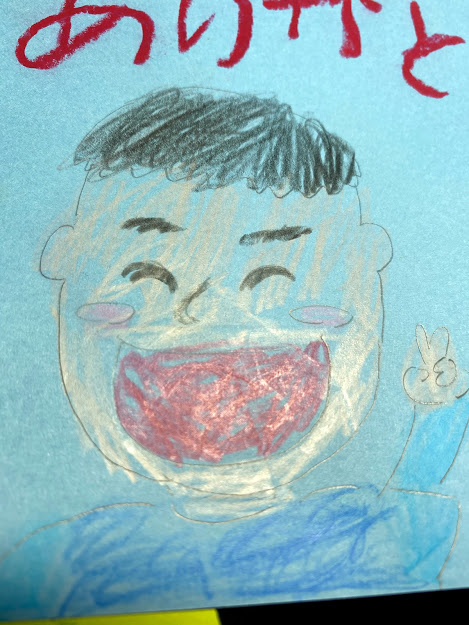
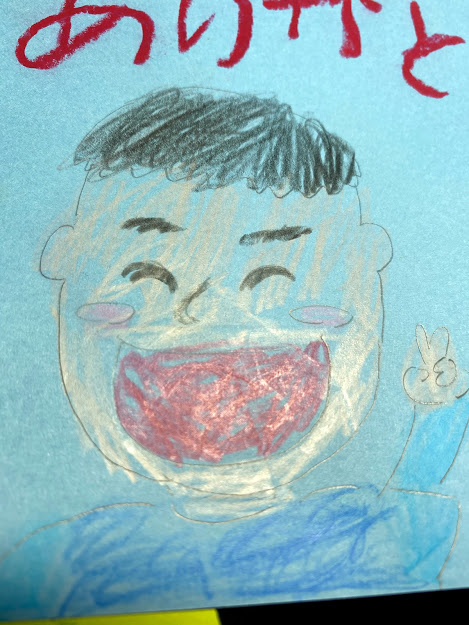
うーん。なるほど。結論から言ってしますと幼児期に鉄棒・跳び箱・マット運動はできなくても良いです!



えっ?!なんで?!
と思った方も多いと思いますが順番に説明していきますね。
幼児期の運動のありかた


まずはこちらをご覧ください。
幼児期は、生涯にわたって必要な多くの運動の基となる多様な動きを幅広く獲得する非常に大切な時期である。動きの獲得には、「動きの多様化」と「動きの洗練化」の二つの方向性がある。
「動きの多様化」とは、年齢とともに獲得する動きが増大することである。幼児期において獲得しておきたい基本的な動きには、立つ、座る、寝ころぶ、起きる、回る、転がる、渡る、ぶら下がるなどの「体のバランスをとる動き」、歩く、走る、はねる、跳ぶ、登る、下りる、這(は)う、よける、すべるなどの「体を移動する動き」、持つ、運ぶ、投げる、捕る、転がす、蹴る、積む、こぐ、掘る、押す、引くなどの「用具などを操作する動き」が挙げられる。通常、これらは、体を動かす遊びや生活経験などを通して、易しい動きから難しい動きへ、一つの動きから類似した動きへと、多様な動きを獲得していくことになる。
「動きの洗練化」とは、年齢とともに基本的な動きの運動の仕方(動作様式)がうまくなっていくことである。幼児期の初期(3歳から4歳ごろ)では、動きに「力み」や「ぎこちなさ」が見られるが、適切な運動経験を積むことによって、年齢とともに無駄な動きや過剰な動きが減少して動きが滑らかになり、目的に合った合理的な動きができるようになる。
引用文献ー文部科学省幼児期運動指針
これは文部科学省の幼児期の運動指針になります。
跳び箱・鉄棒・マット運動という文字は一文も出てきていません。
幼児期に運動面で獲得しておきたいのは
- 動きの多様化
- 動きの洗練化
この2つです
鉄棒・跳び箱・マット運動・縄跳びが出来る出来ないに目を向ける前に、それらをつかった遊びやいろいろな運動が幼児期に大切になってきます。
要するに体育やスポーツにつながる
- 体の土台づくり
- 動きの土台づくり
が必要になってきます。
この2つの土台がしっかりとできてくると鉄棒・跳び箱・マット運動・縄跳びをするときに必要になってくる技術の習得につながっていきます。
3歳から4歳ごろ


次は3歳から4歳の運動についてです。
基本的な動きが未熟な初期の段階から、日常生活や体を使った遊びの経験をもとに、次第に動き方が上手にできるようになっていく時期である。特に幼稚園、保育所等の生活や家庭での環境に適応しながら、未熟ながらも基本的な動きが一通りできるようになる。次第に自分の体の動きをコントロールしながら、身体感覚を高め、より巧みな動きを獲得することができるようになっていく。
したがって、この時期の幼児には、遊びの中で多様な動きが経験でき、自分から進んで何度も繰り返すことにおもしろさを感じることができるような環境の構成が重要になる。例えば、屋外での滑り台、ブランコ、鉄棒などの固定遊具や、室内での巧技台やマットなどの遊具の活用を通して、全身を使って遊ぶことなどにより、立つ、座る、寝ころぶ、起きる、回る、転がる、渡る、ぶら下がるなどの「体のバランスをとる動き」や、歩く、走る、はねる、跳ぶ、登る、下りる、這(は)う、よける、すべるなどの「体を移動する動き」を経験しておきたい。
引用文献ー文部科学省幼児期運動指針
3歳から4歳になると器具を使ったいろいろな運動をすることが大切になってきます。
立つ、座る、寝ころぶ、起きる、回る、転がる、渡る、ぶら下がるなどの体のバランスをとる動きや、歩く、走る、はねる、跳ぶ、登る、下りる、這(は)う、よける、すべるなどの体を移動する動きを経験しておくことで体育やスポーツにつながる運動スキルを身に付けることができます。
鉄棒の逆上がりやマット運動の前回りなど細かかな技術を必要とする技は土台ができる前に細かく指導する必要はありません。
さらに言うと幼児期には技術指導よりも意欲指導を強くすすめます。
体の細かな部分にアプローチするのではなく、体を思いっきり使い、ダイナミックに体を動かすことで心も満たされる運動指導が幼児期に必要になってきます。
4歳から5歳ごろ


次は4歳から5歳になります。
それまでに経験した基本的な動きが定着しはじめる。
友達と一緒に運動することに楽しさを見いだし、また環境との関わり方や遊び方を工夫しながら、多くの動きを経験するようになる。特に全身のバランスをとる能力が発達し、身近にある用具を使って操作するような動きも上手になっていく。さらに遊びを発展させ、自分たちでルールや決まりを作ることにおもしろさを見いだしたり、大人が行う動きのまねをしたりすることに興味を示すようになる。例えば、なわ跳びやボール遊びなど、体全体でリズムをとったり、用具を巧みに操作したりコントロールさせたりする遊びの中で、持つ、運ぶ、投げる、捕る、転がす、蹴る、積む、こぐ、掘る、押す、引くなどの「用具などを操作する動き」を経験しておきたい。
引用文献ー文部科学省幼児期運動指針
4歳からになると友達とのかかわりの中で運動の楽しさを感じてきます。
友だちとの関りがふえてくるのでルールを守たっり、社会性を身に付けたり、運動で多くのことを経験していきます。
例えば2人組になって同じ目的に向かって協力して活動することに楽しさを感じ始める時期でもあります。
5歳から6歳ごろ


次は5歳から6歳です。
無駄な動きや力みなどの過剰な動きが少なくなり、動き方が上手になっていく時期である。
友達と共通のイメージをもって遊んだり、目的に向かって集団で行動したり、友達と力を合わせたり役割を分担したりして遊ぶようになり、満足するまで取り組むようになる。それまでの知識や経験を生かし、工夫をして、遊びを発展させる姿も見られるようになる。この時期は、全身運動が滑らかで巧みになり、全力で走ったり、跳んだりすることに心地よさを感じるようになる。ボールをつきながら走るなど基本的な動きを組み合わせた動きにも取り組みながら、「体のバランスをとる動き」「体を移動する動き」「用具などを操作する動き」をより滑らかに遂行できるようになることが期待される。そのため、これまでより複雑な動きの遊びや様々なルールでの鬼遊びなどを経験しておきたい。
引用文献ー文部科学省幼児期運動指針
5歳から6歳になるころには発達が早い子は複雑な動きができるようになり、さまざまな運動や経験がスポーツや体育に活かされてくるころですね。
できることが増えるようになり、体験すればするほど動きの習得をスムーズに行えることができます。
まとめ


幼児期の運動について文部科学省の運動指針を参考に説明させていただきましたがいかがだったでしょうか?
ブログの題名には幼児期に鉄棒・跳び箱・マット運動はできなくても良いと書きましたが、それらを否定しているのではなく目の前の子どもの発育発達段階を見極めて、ベストなタイミングで段階に合った運動をすることで子どもたちに身につけて欲しいことが獲得できるということです。
鉄棒・跳び箱・マット運動・は特別な技術が必要な体育の種目です。
体育の前に運動やあそびを通じて心と体の土台をつくることが幼児期には必要であるとぼくはいいたいです。
その土台ができてこそ、鉄棒・跳び箱・マット運動の技をやりたいと思える心と体ができてきます。
運動の入り口が技術練習や訓練になってしまっては体を動かす楽しさや心地よさを感じることは難しい。
幼児期に
- 体を動かすことって楽しい!
- 鉄棒・マット・跳び箱を使った運動あそびって楽しい!
と感じる体験でいっぱいになっていれば小学校の体育にもつながっていくと思うのです。
できる、できないよりもできることをとことんすることでいつの間にかできない事にも挑戦しようとする、挑戦できる心と体が育つと思うんです。
意欲のある子には、とことん色々な事にも挑戦させるべきだとも思います。
でも、現場で働かれている保育者の方々はこういったことを知らないことが多いです。
知れば変わる。
たったそれだけのことだと思うのです。
出来る、出来ないに目を向ける前に、できることをとことんやる。
鉄棒・マット・跳び箱をつかって安全に配慮した遊びをとりいれるとちょっと気持ちが楽になるかもしれません。
そんな視点ももっておくと保育の中の運動の見かたや考えかたが変わるかもしれません。
とびっきり楽しい運動あそびプログラムの紹介
この幼児期に運動あそびって楽しい!!!を心と体で思いっきり感じられればしっかりと地面の中に根づいた育ちがあります。
意欲指導の成果はできたできないの技術指導よりも分かりづらい。
でも、子どもたちの長い人生の成長を考えた時に必ず大きな成果に繋がるプログラムをポーラスターでは提供しています。
のぞいてみてくだい^^
大人も子どもも楽しいリーベ式運動あそびプログラム。直接、園へ出向き運動あそび指導


大人のためのこころ・カラダ・技を磨くいつでも遊び研修会